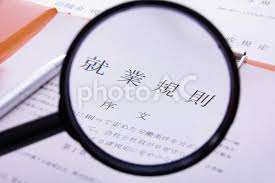就業規則は、労働者の労働条件、職場規律を定めたルールブックです。
この記事では、就業規則についてわかりやすく解説していきます。
就業規則とは職場のルールブック
就業規則とは、会社が従業員の賃金や労働時間などの労働条件や職場のルールを定めたルールブックです。
職場でのルールを定め、双方がそのルールを守ることによって、従業員は安心して働くことができる上、双方のあいだで起きるトラブルを回避できるのです。
就業規則作成のメリット5選
誤解や認識のずれを防止できる
労働条件が明文化されることで誤解や認識のずれを防止できます。
雇用関係の細部まで明確になり、会社と従業員双方が義務と権利を正確に理解できるので、トラブル発生時も円滑な解決が可能となります。
職場の規律が保たれる
全従業員に適用される行動規範が明確化され、職場の規律が保たれます。
統一したルールにより公平性が確保され、従業員間の不公平感を払拭できます。
コンプライアンスの向上
適切に作成された就業規則は会社のコンプライアンスを向上させます。
特に懲戒処分や解雇などの不利益処分を行う際に、その正当性を担保する重要な根拠となります。
労務管理の効率化
人事担当者の判断基準が統一され、一貫した対応が可能になります。
また、新入社員教育や日常の労務管理において参照すべき基準として機能し、業務効率が向上します。
リスク管理
ハラスメント対策や情報管理など重要事項を明確化し、リスクを低減します。
問題発生の対応手順を事前に定めることで、迅速かつ適切な対応が可能となります。
必要な企業は?
就業規則作成が義務付けられているのは常時10人以上の従業員を使用する企業です。
また、新たに就業規則を作成、修正する場合は所轄の労働基準監督署に届け出なければいけません。
就業規則に記載する事項
就業規則には3つの記載事項が存在します。
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」です。
これら三つの記載事項について、詳しく解説します。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、就業規則を作成する際に、絶対に記載しなければならない事項です。
絶対的記載事項には、以下の3点があります。
・労働時間に関する記載事項
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など記載します。
フレックスタイム制、36協定に関する事項、勤怠管理、テレワークの対応などもこの記載事項に含まれます。
労働基準法を遵守し、会社の業務形態や従業員のニーズに合わせて具体的に記載する必要が重要です。
・賃金に関する記載事項
基本給の決定方法や計算方法、支払方法、昇給・降給、割増賃金など記載します。
しかし、この部分は実務的には別途「給与規定」や「賃金規定」で定める場合が多いです。
これらの事項は、従業員自身が賃金がどのように決定され、計算され、支払われるかを理解できるようにすることが重要です。
・退職に関する記載事項
退職手続きや定年制度、解雇、退職金、退職後の手続き、懲戒解雇などについて記載します。
これらの記載事項は、労働契約法や民法などの法令に沿って適正に定め、退職に関するトラブルを未然に防ぐことが重要です。特に解雇関連は、客観的で合理的理由と社会通念上の相当性が求められるので、具体的かつ明確に記載する必要があります。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、就業規則を作成する際に、ルールを定める場合、絶対に記載しなければならない事項です。
相対的記載事項には、以下の8点があります。
・退職金に関する規定
退職金制度の有無、支給対象者、算定方法、支払方法と時期など記載します。
退職金は労働者の長期勤勤続の対価であり重要な労働条件となるため、明確かつ公平な基準を設けることが重要です。
・臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関する規定
特別手当、一時金などの支給条件や要件、賞与の支給回数・支給月、最低賃金の遵守に関しての基本方針・是正方法など記載します。
これらの記載事項の中で、特に賞与に関しては、多くの企業で重要な報酬要素となっているため、支給条件や算定方法を明確に定めておくことが会社と従業員間のトラブル防止につながります。
・食費や作業用品などに関する規定
食事手当の有無、会社支給の作業用品の種類と数量、会社負担と個人負担の明確化など記載します。
特に賃金からの控除を行う場合は、労働基準法第24条に基づいて、労使協定の締結が必要となる点にも注意が必要です。
明確かつ公平な負担関係を定めることで、労使間のトラブルを未然に防ぎ、従業員の納得感を高めることができます。
・安全衛生に関する規定
安全衛生委員会の設置などの安全衛生管理体制、安全衛生教育、健康管理、災害防止、作業環境管理、従業員の遵守事項、疾病の予防と対応、労働災害発生時の対応など記載します。
これらの事項は、労働安全衛生法の遵守と従業員の安全と健康を確保するために重要です。
就業規則に適切に記載し、実効性のある安全衛生管理を行うことで、労働災害発生の防止と従業員の健康維持・増進につながります。
・職業訓練に関する規定
教育訓練制度の概要、能力開発支援、キャリア形成支援、社外研修・留学制度、訓練費用の返還、技能実習制度など記載します。
従業員のスキルアップとキャリア形成を支援するとともに、会社の人材育成戦略を具体化するものです。
明確な訓練制度を定めることで、従業員の成長意欲を高め、企業の競争力強化にもつながります。
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する規定
労災保険給付の種類と申請手続き、通勤災害の補償、業務外傷病の扶助、福利厚生制度、職場復帰支援、遺族補償、第三者行為災害、災害補償に関する窓口相談など記載します。
従業員が安心して働ける環境を整備するうえで重要な要素です。
業務上の災害については労働基準法75条以下に基づく災害補償義務があり、また業務外の傷病についても福利厚生の観点から適切な支援制度を定めることが求められます。
就業規則に明確に記載することで、従業員の生活保障と早期復職を促進することにつながります。
・表彰及び制裁に関する規定
表彰制度、制裁の種類と定義、懲戒事由、懲戒手続き、懲戒の公平性・透明性確保、制裁に伴う処遇、再発防止措置、刑事事件との関係など記載します。
これらの事項は、従業員の模範的行為を推奨するとともに、職場秩序を維持するために重要です。
特に制裁については、予見可能性と公平性を確保するため、できるだけ具体的に記載することが求められます。
また、懲戒権の濫用とならないよう、適正な手続きと相当性の原則に配慮した制度設計が必要です。
・休職に関する規定
休職制度の概要、休職事由、休職期間、休職手続き、休職中の賃金・処遇、復職、休職中の就業制限、休職期間満了時の措置など記載します。
これらの事項は、労働契約の一時的な変更を伴う休職制度の適正な運用のために重要です。
特に私傷病休職については、復職の可能性を含めた明確な基準を定めることで、従業員の雇用の安定と会社の人事管理の適正化を図ることができます。
また、休職制度は法定の休暇・休業(育児・介護休業など)との関係を整理して記載することも重要です。
任意的記載事項
任意的記載事項は各々の企業で判断を任せられる記載事項です。
記載内容は会社の理念や社是など多岐に渡ります。
これらは労使間のトラブルを回避するうえで、また人事戦略を遂行する上で非常に重要な記載事項です。
就業規則作成の流れ
就業規則の作成・変更
事業所の実情に沿った「就業規則」を作成する。
以下のリンク先には、厚生労働省が掲示した「モデル就業規則」があるので、参考にしてください。
労働組合の過半数または労働組合過半数代表者の意見を聴取
就業規則の一部のみを変更する場合にも、労働者の過半数代表者の意見を聴く必要がある。
また、一部の労働者のみに適用される就業規則を作成または変更するにあたっても、当該事業場の全従業員の過半数を代表者等の意見を聴かなければならない。
就業規則届または変更届を記載(意見書の添付も必要)
就業規則を作成または変更した場合、届け出を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
就業規則を届け出る場合には、従業員の過半数を代表するものの氏名を記載した意見書を添付しなければならない。
従業員へ周知する
就業規則は届け出をしただけでは効力が生じない。
従業員に周知して初めて法的効力が生じる。
考えられる就業規則関連のトラブル
就業規則がない場合や、不備がある場合に考えられるトラブルを実際の事例に基づいて紹介します。
解雇したのに「無効」となったケース
ある企業で、社員が度重なる遅刻・無断欠勤を理由に「解雇」した。
しかし、就業規則に解雇事由が記載されておらず、社員から「不当解雇」と訴えられ、裁判で会社側が敗訴したケースがある。
ハラスメントで訴えられたが、社内で対応できなかった。
上司によるパワハラで社員がメンタル不調になった。
相談窓口もなければ、ハラスメント規定もなかったため、会社は対応できず、労基署に通報され調査対象になった。
副業がバレて揉めたが、禁止規定がなかった。
社員がSNSで副業を宣伝していたことが発覚。
上司が「会社に無断で副業するな」と注意したが、社員側は「就業規則に副業禁止事項は記載されていない」と反論。
結果的に注意も処分もできなかった。